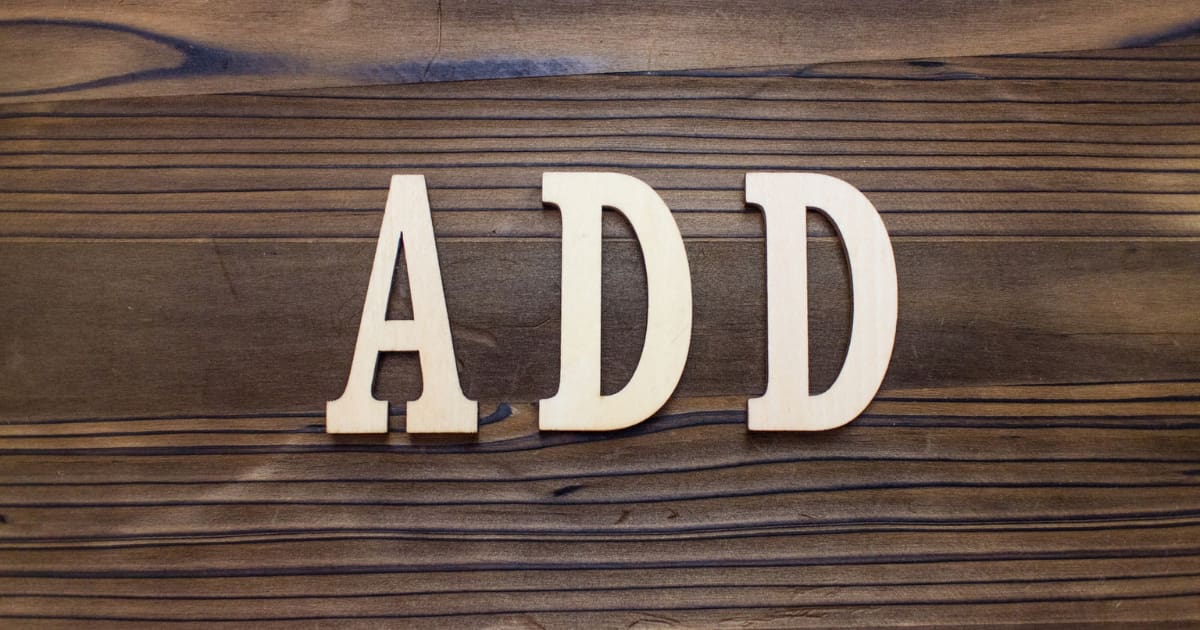年齢を重ねるにつれて、「最近スマホの文字が見えにくくなった」「手元のピントが合いにくい」と感じることはありませんか?こうした視力の変化は、誰にでも起こる自然な現象ですが、見え方に違和感があると、日常生活のちょっとした場面でストレスを感じやすくなります。
そんなときに目にするのが、コンタクトレンズの「ADD」という表示。しかし、「これは一体何の数値?」「どう選べばいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、コンタクトレンズにおけるADDの意味や役割、必要になるタイミング、そして自分に合った選び方までを、視力に悩む大人の方に向けてやさしく解説していきます。
ADDとは何?コンタクトレンズの「追加度数」を知ろう
コンタクトレンズを選ぶ際、「ADD」という表示を目にして戸惑った経験はありませんか?これは、遠近両用レンズを使用する際に欠かせないパラメーターで、視力の変化に合わせて「近くを見る力」を補うための度数です。
ここでは、ADDとは何か、そしてどのような場面で必要になるのかを丁寧に解説していきます。
ADD=追加度数。どういうときに必要になるの?
ADD(アディション)とは、遠近両用コンタクトレンズにおける「近距離視力を補うための追加度数」のことです。通常の度数が遠くを見るためのものだとすれば、ADDは手元を見る力を補う役割を持っています。
この追加度数が必要となるのは、加齢によって目のピント調整機能が弱まり、近くのものが見えにくくなってきたときです。特に40代以降になると、その兆候を感じる方が増えてきます。
▼ADDが必要とされる主なシーン
| シーン例 | 見えにくさの内容 |
| スマホや本を読むとき | 小さな文字がかすむ、焦点が合いにくい |
| 書類作業で長時間手元を見続けたとき | 目が疲れやすい、ピントを合わせるのがつらい |
| 料理や手芸などの細かい作業をするとき | 手元がぼやける、集中しにくい |
これらのシーンで「見えにくい」「疲れやすい」と感じるなら、ADD付きのコンタクトレンズを検討する価値があります。目の変化は少しずつ進行するため、早めに気づき、適切な度数で補正することが快適な生活につながります。
近くが見えづらくなる理由とADDの関係
年齢を重ねると、以前ははっきり見えていた手元がぼやけて感じるようになります。これは、加齢にともなって目の水晶体が硬くなり、ピント調整が難しくなる「老視(ろうし)」が原因です。老視は、誰にでも起こる自然な現象で、40歳前後から少しずつ進行します。
この視力の変化に対応するために用いられるのが「ADD(追加度数)」です。ADDは、近くを見るために必要な焦点距離をサポートする役割を担っており、老視による不便さを補ってくれます。
▼老視の進行と見え方の変化
| 年齢の目安 | 見え方の変化例 | 必要となる補正方法 |
| 40歳 | 小さな文字が読みにくくなる | +1.00 |
| 45歳 | 遠くから近くに焦点を切り替えにくい | +1.50 |
| 50歳 | 長時間の近距離作業で疲労感が強くなる | +2.00 |
| 55歳 | さらに手元が見えづらくなる | +2.50 |
| 60歳 | 強い補正が必要になることも | +3.00 |
このように、年齢によって見え方が変わるのは自然なこと。ADDを上手に使うことで、老視の不便さを軽減し、仕事や日常生活での快適さを保つことができます。
ADDの数値ってどう読むの?よくある表記も紹介
コンタクトレンズのスペックに記載されている「+1.00」「+1.50」などの数値、これがADD値です。ADD値は、どの程度の近距離補正が必要かを示すもので、老視の進行度に応じて段階的に設定されます。
ただし、すべてのレンズが数値で表示されているわけではありません。中には、「Low(低)」「Med(中)」「High(高)」と表記されることもあり、製品によって意味合いが異なる場合もあるため注意が必要です。
▼ADD値の表記とその目安
| 表記 | 数値の目安 | 老視の進行レベル |
| Low | +0.75〜+1.25 | 初期(40代前半〜中盤) |
| Mid/Med | +1.50~+1.75 | 中程度(40代後半〜50代) |
| High | +2.00〜+2.50 | 進行期(50代以降) |
※メーカーごとに違いがあるため、製品情報をご確認ください。
ADDの数値は、ただ数値が高ければ良いというものではなく、「見えやすさ」「慣れやすさ」「ライフスタイルとの相性」によって選ぶべき範囲が異なります
。たとえば、スマホやPC作業が多い方は近距離に強い補正を求める傾向がありますが、強すぎると逆に遠くが見づらくなることもあるためバランスが重要です。
遠近両用コンタクトレンズとADDの深い関係
ADDは、遠近両用コンタクトレンズに欠かせないパラメータです。遠くも近くも快適に見えるよう設計されたこのレンズには、見え方のバランスを保つために精密な度数調整が必要となります。
ここでは、遠近両用レンズの基本的な仕組みと、ADDがどのように関係しているのかをわかりやすく解説していきます。
遠近両用レンズとは?どんな仕組み?
遠近両用コンタクトレンズには、中心近用デザイン、累進屈折型、3重焦点型などの設計があります。「同心円型」「累進焦点型」という2分類だけでなく、さまざまな設計タイプが存在します。
▼代表的な遠近両用レンズの構造タイプ例
| タイプ | 特徴 |
| 中心近用デザイン | レンズ中央に近用度数、周辺に遠用度数を配置する設計 |
| 累進屈折型(マルチフォーカル) | 度数が段階的に変化し、自然なピント調整がしやすい設計 |
| 3重焦点型 | 遠用・近用・中間用の度数が分布し多焦点で広い見え方が可能 |
どのタイプでも、ADDが正しく設定されていることで、スムーズなピント移動や自然な視界が実現されます。逆に、ADDが合っていないと、手元がぼやけたり、遠くの景色がかすんだりといった不快感の原因にもなります。
遠近両用レンズは、老眼鏡のようにかけ外しの手間がなく、見た目にも違和感が少ないのが魅力です。見え方の設計が非常に繊細なため、自分の目に合ったタイプとADD値を選ぶことが、レンズの効果を最大限に引き出すカギになります。
ADD値が快適な見え方を左右する理由
遠近両用レンズの見え方の快適さを大きく左右するのが「ADD値の設定」です。ADD値が適切であれば、遠くから手元への視線移動もスムーズで、自然な見え方が維持されます。
しかし、ADD値が強すぎたり弱すぎたりすると、さまざまな違和感が生じることがあります。
▼ADDが合わないと起こりやすい見え方のトラブル
- 手元がぼやける
- 焦点が合うまでに時間がかかる
- 遠くを見るときに違和感を感じる
- めまいや目の疲れが出る
これらの症状は、レンズの質ではなく、度数設定のズレが原因で起こっているケースがほとんどです。特に遠近両用レンズは、遠距離・中間距離・近距離のすべてをカバーする設計であるため、微細な度数の違いが見え方に影響を与えます。
生活スタイルによって適したADD値は変わります。たとえば、デスクワーク中心の方は手元重視、外回りや運転が多い方は遠く重視といったように、使用シーンに合わせた調整が必要です。
遠近両用レンズ選びで失敗しないためのポイント
遠近両用レンズは便利な反面、選び方を間違えると「思ったより見えにくい」「使いづらい」と感じてしまうことがあります。
そうならないためにも、購入前に以下のポイントを確認しておきましょう。
▼遠近両用レンズ選びのチェックポイント
- 必ず眼科で視力検査を受ける
- ライフスタイル(PC時間、屋外活動など)を伝える
- 初めは低めのADDから試す
- トライアルレンズで見え方を確認する
- 違和感がある場合はすぐに調整を相談する
とくに、遠近両用レンズは“慣れ”が必要なアイテムです。はじめから完璧な見え方を求めるのではなく、徐々に目を慣らしていく意識が大切です。また、使用中に違和感を覚えた場合は、無理せずすぐに眼科で再チェックしてもらいましょう。
自分に合ったADD値の見つけ方と注意点
遠近両用コンタクトレンズで快適な見え方を得るには、ADDの値が自分に合っていることが大前提です。しかし、単純に年齢や視力だけで決まるものではなく、生活習慣や使用環境によって最適な度数は変わってきます。
ここでは、ADD値の選び方と使用時に注意すべきポイントについて、わかりやすく解説します。
最適なADDを知るには?検査とライフスタイルの関係
ADD値を決める際には、視力検査による数値的なデータだけでなく、生活スタイルや見え方の希望も重要な判断材料になります。単に「老眼が進んだから強い度数が必要」とは限らず、使用シーンによって必要な補正度合いは異なります。
そのため、眼科での検査の際は、ただ視力を測るだけでなく、自分の1日の生活パターンや見えにくさを感じる場面についても、できるだけ具体的に伝えることが大切です。
▼生活スタイル別・ADD設定の参考ポイント
| 主な生活スタイル | 適したADDの傾向 | 理由 |
| デスクワーク中心 | やや強めのADDを希望する傾向あり | 手元の見え方を重視するため |
| 外回り・運転が多い仕事 | 弱め〜中程度のADDが選ばれやすい | 遠距離視野のクリアさを優先したいため |
| 読書・手芸など近距離作業中心 | 中〜強めのADDが必要になることも | 長時間近くを見るため、強い補正が必要になる場合も |
このように、「自分がどの距離を重視したいのか」を考えることで、よりフィットしたADD設定ができます。医師としっかり相談し、見え方の要望を伝えることで、数値だけに頼らない“本当に快適な見え方”が実現できます。
レンズの種類別に見るADDの違い
同じADD値でも、使用するコンタクトレンズの種類によって、実際の見え方が異なることがあります。これは、レンズの設計や素材の違いが、度数の感じ方やピントの合い方に影響するためです。
使いやすさやコスト、フィット感といった点でも選び方が変わってくるため、ADDの数値だけでなく、レンズタイプとの相性も意識することが重要です。
▼レンズの種類とADDの使用感の違い
| レンズの種類 | 特徴 | ADDとの相性の特徴 |
| 1日使い捨てタイプ | 手軽で衛生的。初心者に人気 | 比較的ソフトな設計で慣れやすいが、視界はやや控えめなことも |
| 2週間・1ヶ月交換タイプ | コストパフォーマンスが高い。安定性も良好 | 設計のバリエーションが多く、調整幅が広い |
| ハードレンズ | 視力矯正力が高く、安定した視界が得られる | 見え方がシャープだが、慣れるまでに時間がかかる場合もある |
使用感に違和感を覚えたときは、ADD値ではなくレンズの種類を変えるだけで改善するケースもあります。どのレンズにも一長一短があるため、複数のタイプを試してみることで、自分に最適な見え方に近づくことができます。
使ってみて違和感があるときは?対処法を紹介
遠近両用コンタクトレンズは、構造が特殊な分、慣れるまでに時間がかかることがあります。特に使い始めの数日は、「少しぼやける」「視線を動かすと違和感がある」といった症状が出ることもありますが、これは一定の範囲では正常な反応です。
ただし、1〜2週間使用しても改善しない場合や、日常生活に支障が出るような見え方であれば、何かしら調整が必要なサインかもしれません。
▼違和感を感じたときのチェックポイント
- ADD値が強すぎる or 弱すぎる
- レンズの種類が合っていない
- 使用時間が長すぎて目が疲れている
- 眼の乾燥や装着ミスが影響している
こうした違和感の原因は1つとは限らず、複数の要素が重なって起きていることも少なくありません。対処法としては、まずは使用時間を短くして目を慣らしつつ、違和感が続く場合は眼科での再評価を受けましょう。
少しの違和感でも放置していると、目の疲労やストレスにつながる可能性がありますので、快適に使い続けるためにも“早めの対応”が安心です。
まとめ
コンタクトレンズにおけるADDとは、近くを見るために必要な追加の度数を意味し、特に遠近両用レンズで重要な役割を果たします。40代以降、老視の進行により手元の見えづらさを感じ始めたら、ADD値の適切な設定が快適な生活のカギとなります。
遠近両用レンズにはさまざまな設計や種類があり、使用者のライフスタイルや目の状態に応じて最適な選択が異なります。単に数値だけで判断するのではなく、生活シーンを想定したうえで眼科医と相談しながら選ぶことが大切です。
また、使用開始後に違和感がある場合は無理に慣れようとせず、ADD値やレンズの種類を見直すことで解決できることもあります。遠近両用レンズを諦めていた方も、この記事を参考に自分に合うレンズを探してみてはいかがでしょうか。